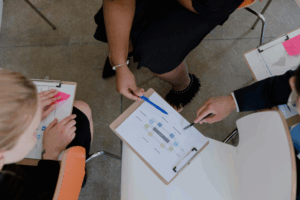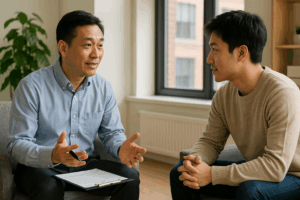はじめに
いまは、AIが素早く下書き、場合によっては完成品を一瞬で作ってくれる時代です。けれど、完成品が立派でも、自分の実力が育っているとは限りません。 人生には“ごまかしの効かない勝負どころ”があります。そういう場面で、あなたはどう備えますか。
一方で、AIを活用した学び直しは、時間・場所・コストの面で優れた方法でもあります。
仕事の改善、英語のやり直し、資格取得、家計やキャリアの見直し——大人の学びで本当に必要なのは、自分で選び、直し、活かす力です。本稿では、AIの力を借りつつ、それを自分の実力に変えていく方法を、コーチングの視点でわかりやすく整理します。
鍵は次の4つです。
① 自己説明 ② 比較 ③ 転移 ④ プロセス可視化
これはプログラミングに限らず、英語学習や日々の仕事の課題にも同じように効果があります。
なぜAIだけでは不十分なのか
AIは「材料出し」や「雛形作成」が得意です(2025年9月現在)。いわば強力な“下書きエンジン”。しかし、最終的にそれを使いこなす判断や文脈への当てはめは、私たちの役目です。
例えば、家計改善を考える場面でAIに相談すると、「まずは保険料と通信費を削減しましょう」といった一般的な提案が返ってきます。確かにこれは雛形としては有効ですが、実際には家庭ごとに事情が異なります。すでに格安SIMを利用して通信費が最小限の家庭では、通信費の見直しは意味を持ちません。逆に、小さな子どもがいる家庭では、保障を重視しているため保険の解約は不適切かもしれません。その場合は、光熱費の節約や教育費の積み立てを優先するほうが現実的です。
このように、AIの提案を「材料」として受け取り、自分の生活状況や目標に合わせて優先順位を付け直すことが、AIを相棒として活かす第一歩になります。
学びのフレーム:4つの観点
① 自己説明——「なぜそうしたか」を自分の言葉で
「自己説明」とは、学んだことや選んだ行動について“なぜそうしたのか”を自分の言葉で説明することです。AIが出してくれた答えをそのまま受け入れるのではなく、採用や修正の理由を言葉にすることで、理解が深まり、次の選択も速くなります。
やり方はシンプルです。AIから提案を受けたら、下記について一言メモにするだけです。紙でもスマホでもよく、文章にまとめる必要はありません。「なぜ?」に答える短い言葉があれば十分です。
- どこを採用したか
- どこを直したか
- その理由は何か
具体例
- 英会話
AIが「I appreciate your help.」と出したときに、「なぜ appreciate を選ぶのか? thank you との差は?」と考えてみる。相手との関係や場面に応じて「フォーマルに感謝したいから appreciate」と理由を残せば、次の場面で迷いません。 - 家計改善
AIが「通信費を見直しましょう」と提案しても、すでに格安SIMを使っている家庭では優先度が低い。そこで「通信費は既に削減済み。代わりに光熱費を見直す」と自己説明すれば、判断の軸が明確になります。 - 仕事
会議で出された複数案のうち、提案Aを採用してBを捨てたなら、「実現可能性が高いからA」「コストがかかりすぎるからBは見送り」と理由を一言添える。これを繰り返すことで、判断基準が積み上がっていきます。
ポイント:自己説明は、「理由を書く=理解が深まる」というシンプルな仕組みです。小さな理由付けを積み重ねると、自分の中に判断軸ができ、AIの提案を使いこなす力がぐっと高まります。
② 比較——評価軸で別案をくらべる
「比較」とは、AIの提案や自分の案、複数の選択肢を**同じ基準(評価軸)**で並べて見比べることです。雰囲気や直感だけで決めるのではなく、「何を優先するのか」という物差しを先に決め、その基準に沿って案を評価します。やり方はシンプルで、下記の流れです。
- 軸を決める(例:コスト、スピード、正確さなど)
- 各案をその軸で採点する(◎/○/△ でも十分)
- 総合して選ぶ
具体例
- 英会話
「Thank you」と「I appreciate it」を比べるときに、軸を「丁寧さ/直接性/誤解リスク」に設定。ビジネス文書なら「丁寧さ」で appreciate に軍配が上がり、気軽な場では thank you が適切と判断できます。 - 家計改善
AIが「保険見直し」と「外食費削減」を提案したとします。このときの軸は「効果(金額インパクト)/継続性(習慣にできるか)/リスク(生活への影響)」に設定。結果として「外食費削減は継続性が高くリスクも低い」と判断できれば、取り組む優先順位が明確になります。 - 仕事
提案A(新システム導入)と提案B(既存システム改善)を比較するとき、軸を「効果/コスト/リスク/継続性」に設定。大きな効果が見込めてもコストとリスクが高すぎるなら、提案Bを選ぶ根拠になります。
ポイント:比較は、軸を決めてから考えることが大切です。軸が定まっていれば、場面が変わっても判断がぶれにくくなり、迷いが減ります。AIが出した複数案に対しても、「どちらが好きか」ではなく、「どの軸で優れているか」で判断できるため、再現性のある意思決定につながります。
③ 転移——条件を変えても使えるか確かめる
「転移」とは、学んだことを別の場面や条件でも応用できるかどうかを確かめることです。単に覚えただけでは“その場限り”になりがちですが、条件を少し変えて試すことで「本当に使える学び」に変わります。やり方は次の通りです。
- 一度身につけたことを、別の場面にあてはめる
- 違いに気づき、修正点を洗い出す
- 共通するパターンを見つける
具体例
- 英会話
「Thank you for your support.」を覚えたら、同じ意味を「友人宛」「上司宛」「取引先宛」で書き分けてみる。友人にはカジュアルに「Thanks a lot!」、上司には「I really appreciate your guidance.」、取引先には「We sincerely appreciate your continued support.」と変えることで、表現を状況に応じて転移させられます。 - 家計改善
「外食費を減らす」取り組みがうまくいったら、次は「光熱費の節約」や「サブスク整理」に応用する。最初に使った「効果/継続性/リスク」で比べる軸をそのまま当てはめれば、別分野でも判断できるようになります。 - 仕事
提案が一部署で成功したら、別部署や別の顧客にスモールテスト(2週間程度)として導入する。条件が違う中で調整点を見つけられれば、組織全体への展開につながります。
ポイント:転移は「学びがその場で終わらない」ための仕上げです。場面を変えて試すことで、応用力の芽が見え、知識やスキルが「本当に使えるもの」へと育ちます。AIの提案も、転移を通して検証することで、あなた自身の判断力や適応力に変わっていきます。
④ プロセス可視化——途中経過を残してテコ入れ
プロセス可視化とは?どうやるのか
「プロセス可視化」とは、最終成果物だけでなく、途中でどんな試行や修正をしたのかを“見える形”で残すことです。やりっぱなしにせず、後から振り返れる証拠を軽くメモしておくことで、改善の方向が具体的になります。
やり方は難しくありません。
- 最初の出力(AI案や自分の初稿)を保存する
- どこを修正したかを一言メモする
- 失敗やエラーも残しておく(「何がダメだったか」を短く書く)
具体例
- 英会話
- AIが出した英文「I appreciate your kindness.」を初稿として残す。
- 修正版「I really appreciate your support with this project.」と修正理由(より具体的にした)を一言メモ。
- 誤り例も「I appreciate to help you. → 不自然」と残しておけば、次に同じミスを避けられます。
- 家計改善
- 「通信費削減案」を最初に検討したが「すでに格安SIM利用済みで効果なし」と記録。
- その後「光熱費見直し」に切り替え、「季節別の電気代比較をした」と修正点を残す。
- 失敗した施策(サブスク解約→家族の反発あり)も残しておくと、次は「合意形成の工夫が必要」と改善に活かせます。
- 仕事
- 新提案A(導入コストが高すぎて却下)→「理由:コストが見合わない」と記録。
- 代替案B(既存ツール改善)を採用したプロセスを残す。
- 途中の失敗(顧客ヒアリング不足で仕様がずれた)を残しておくことで、次回はヒアリング強化という改善点がはっきりします。
ポイント:成果物だけでは、「なぜ今の形になったのか」が分かりません。プロセスを軽く可視化しておくと、次に取り組むときの改善点が具体的に見え、同じ失敗を繰り返さなくなります。つまり「やりっぱなし」から「積み重ねる学び」に変わるのです。
おわりに
AIは材料出しや雛形作成に強みがあります。しかし、それを自分の実力に変えるには、①自己説明 ②比較 ③転移 ④プロセス可視化という4つのフレームが欠かせません。
- 自己説明で理解を深め、
- 比較で判断基準を磨き、
- 転移で応用力を鍛え、
- プロセス可視化で改善を積み重ねる。
このサイクルをコーチングの視点で回していけば、AIはただの便利ツールではなく、学び直しの強力な相棒になります。プログラミングにも、英語学習にも、家計や仕事にも、この4つのフレームはそのまま活かせます。
学び直しは、AIと自分の思考を組み合わせて「実力」に変えること。 今日から試せる小さな工夫で、次の一歩を確実に踏み出せます。
参考文献
Chi, M. T. H., de Leeuw, N., Chiu, M. H., & LaVancher, C. (1994). Eliciting self-explanations improves understanding. Cognitive Science, 18(3), 439–477.
Schwartz, D. L., & Bransford, J. D. (1998). A time for telling. Cognition and Instruction, 16(4), 475–522.
Barnett, S. M., & Ceci, S. J. (2002). When and where do we apply what we learn? A taxonomy for far transfer. Psychological Bulletin, 128(4), 612–637.
Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7–74.
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.
執筆者プロフィール
岳野 公人(たけの・きみひと)
滋賀大学教育学部教授。1994年長崎大学教育学部卒業(古谷吉男教授に師事)。1999年兵庫教育大学連合大学院(博士課程)中途退学(松浦正史教授に師事)。1999年金沢大学教育学部講師。2003年兵庫教育大学連合大学院において学校教育学博士を取得。2015年より現職。
南山教育研究所より|所長 南山紘輝のメッセージ
AIが一瞬で答えや下書きを出してくれる時代になりました。だからこそ、私たちが磨くべきは「答えをどう受け止め、どう活かすか」という力です。便利な道具が増えても、人生の本当に大切な場面では、自分の判断・言葉・行動が試されます。学び直しは、その力を鍛え直す機会です。AIは強力なパートナーですが、それをどう組み合わせ、自分の中に積み上げていくかは一人ひとりに委ねられています。南山教育研究所は、「AI時代にあっても、人が自分の軸を育み、未来を切り拓いていく」ことを大切にしています。学びとは、情報を増やすことではなく、選び、つなぎ、活かすこと。そして、それを通して自分の人生を確かなものにしていくことです。どうかAIに振り回されるのではなく、AIを相棒にしながら、自分自身の力を信じて歩んでください。その歩みこそが、どんな時代でも揺るがないあなたの実力になります。