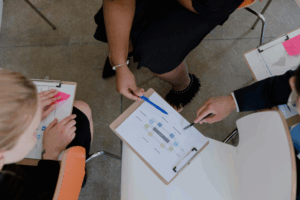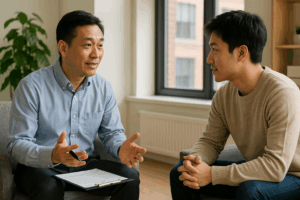生成AIと学びの関係を考える
先日、ある教育ワークショップで「初心者向けアプリ制作体験」を見学する機会がありました。内容は、生成AIを利用して既存のアプリケーションの一部を改変しながら、自分なりのアプリを作っていくというものです。
ところが、予想以上に注目を集めていたのは、ChatGPTなどの生成AIを使う参加者の姿でした。 「このアプリを作るコードを教えて」と入力すれば、数秒で必要なコードが生成され、それをコピペすればアプリは動く。確かに成果物は完成します。しかし、ある参加者は正直にこう漏らしていました。
「正直、自分は何も学んでいない気がする」
この場面は、生成AIの二面性を象徴しているように思えます。AIは便利で効率的である一方で、学習者が自分で思考し、試行錯誤する機会を奪ってしまう可能性があるのです。では、生成AIを学びに取り入れるとき、どのような使い方が望ましいのでしょうか。
ここで手掛かりとなるのが認知心理学です。1960年代以降に発展してきたこの分野は、人間の思考を「情報を処理する装置」としてモデル化し、その仕組みを明らかにしてきました。こうした知見は、学習過程の理解だけでなく、コンピュータやAIの技術発展にも大きく貢献しています。
さらに私は、生成AIと並んで「コーチング」が学びを支える重要な役割を果たせるのではないかと感じています。AIの利便性と、コーチングがもたらす人間的な対話や振り返り。この二つをどのように組み合わせて活用できるのか。ここから先では、その可能性について考えてみたいと思います。
生成AI活用のメリットとデメリット:アプリ制作の場合
ここでは、認知心理学の考え方をアプリづくりに応用したときの良い点と注意点を、簡単にまとめています。
1. 認知的負荷の調整
学習者のワーキングメモリには容量の限界がある(Sweller, 1988)。複雑なプログラムを書くとき、文法やエラー処理にばかり注意を取られてしまうと、本来学びたい「設計意図」や「機能構築」には十分にリソースを割けない。AIはこうした部分を補助し、不要な負荷を軽減してくれる。
しかし一方で、AIがすべてを提示してしまうと「生成効果」(Slamecka & Graf, 1978)が得られず、自分でコードを生み出す経験を欠いたまま理解が表層的になってしまう。学びに必要なのは「程よい負荷」であり、AIがそのバランスを崩すリスクを持つ。
2. メタ認知と学習の自己調整
学習者が「自分はどこまで理解できているのか」を把握するメタ認知は、学習の成否を左右する(Flavell, 1979)。AIとの対話は、自分の理解度を確認する良い手段となる。しかし、AIが常に答えを与える環境では、誤答の原因を自ら分析する機会を失い、メタ認知力が鍛えられない。つまり「理解したつもり」の錯覚に陥る危険がある。
3. 動機づけと自己効力感
AIを活用して短時間で成果物が完成すれば、大きな達成感を得られる。これは学習意欲を高める有効な要因である(Bandura, 1997)。だが、長期的には「AIがなければできない」という依存感が芽生え、自己効力感を損なうリスクがある。生成AIは学習者を勇気づける存在にもなり得るが、同時に自律的な力を奪う存在にもなり得る。
生成AIを学習に取り入れると、認知的負荷の調整・メタ認知の促進・動機づけの向上といった利点がある一方で、負荷の欠如による浅い理解や自己効力感の低下といった課題も生じます。大切なのは、AIに頼りすぎず「学習者自身が考え、調整する余地」を残すことです。AIはあくまで学びを支える補助輪であり、主役は常に学習者自身なのです。
適切な生成AI活用のデザイン
これらを踏まえると、学習における生成AI活用のポイントは「答えを出す道具」ではなく「思考を支援する伴走者」として使うことにあります。
具体的には、以下のような工夫が考えられます。
- 部分的支援:コード全体を生成させるのではなく、関数の骨組みやエラー修正のヒントに限定する。
- 自己説明の促進:AIが提示したコードをそのまま使うのではなく、「なぜこの書き方なのか」を自分で解説する課題を組み込む。
- 比較学習:AIに複数の実装方法を提示させ、それぞれの利点・欠点を学習者が批判的に比較する。
こうした方法により、AIは学習者の思考を置き換えるのではなく、拡張する方向で機能する可能性があります。
生成AIによる補助とコーチングによる補助の対比
ここで興味深いのは、生成AIによる補助と人間のコーチングによる補助との違いです。両者は似て非なる支援の形を持っているようです。
1. 情報の即時性 vs. 内省の促進
- 生成AI:即座に情報を返すことで、停滞を防ぐ。効率は高いが、思考の時間を奪う場合がある。
- コーチング:問いかけを通じて学習者自身に考えさせる。時間はかかるが、内省と自己発見を促す。
2. 認知的負荷の扱い
- 生成AI:不要な負荷を削ぎ落とす役割を果たすが、負荷をゼロにしてしまうリスクがある。
- コーチング:敢えて適度な負荷を与え、思考の深まりを促す。学習者に「伸びる痛み」を経験させる。
3. 自己効力感の源泉
- 生成AI:成果物の完成を通じて短期的な達成感を提供する。
- コーチング:自分で答えを導いた経験を重視し、長期的な自己効力感を育む。
このように、生成AIは「即時性」と「効率」に優れ、コーチングは「内省」と「長期的成長」に強みを持つようです。両者を対立的に捉えるのではなく、場面に応じて組み合わせることが、今後の学びや成長のサポートには必要だろうと感じます。
結論:生成AI時代の学びをデザインする
アプリ制作WSでの「丸写し体験」が示したように、生成AIは使い方次第で「何も学ばない経験」にも「大きな成長の契機」にもなります。認知心理学の視点から整理すると、AIは認知的負荷の調整、メタ認知の支援、動機づけの促進といった面で有効である一方、浅い理解、依存、批判的思考の低下といったリスクもはらんでいます。
したがって学びや成長のサポート場面では、生成AIを「便利な答え製造機」としてではなく、学習者の思考を引き出す補助的なパートナーとして位置づける必要があります。さらに、AI支援と人間によるコーチング支援を対比し、それぞれの長所を活かしながら学習環境を設計することが、これからの学びのデザインに求められる姿勢であろうと考えています。
参考文献
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906–911.
Slamecka, N. J., & Graf, P. (1978). The generation effect: Delineation of a phenomenon. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 4(6), 592–604.
Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285.
執筆者プロフィール
岳野 公人(たけの・きみひと)
滋賀大学教育学部教授。1994年長崎大学教育学部卒業(古谷吉男教授に師事)。1999年兵庫教育大学連合大学院(博士課程)中途退学(松浦正史教授に師事)。1999年金沢大学教育学部講師。2003年兵庫教育大学連合大学院において学校教育学博士を取得。2015年より現職。
南山教育研究所より|所長 南山紘輝のメッセージ
生成AIの登場によって、学びの在り方は大きく変わりつつあります。AIは効率的に答えを提示してくれる一方で、学習者から「自分は何も学んでいない気がする」という声が聞かれることもあります。学びには「程よい負荷」と「自ら考える余地」が欠かせず、すべてをAIに委ねてしまうと、その大切なプロセスが損なわれる可能性があるのです。しかし同時に、AIは不要な作業を減らし、本質的な思考に集中できるよう支えてくれる存在でもあります。つまり、AIを「答えを与える道具」としてではなく「思考を拡張する伴走者」として位置づけることで、学びはより豊かなものとなり得るのです。ここで重要なのが、人によるコーチングとの補完関係です。AIは即時性と効率に優れていますが、コーチングは問いかけを通じて内省を促し、学習者の自己効力感を育みます。両者を対立的に捉えるのではなく、場面に応じて組み合わせることが、これからの教育や人づくりに求められる視点だと考えています。本稿が、皆さんのAI活用やコーチング実践に新たな気づきをもたらし、広い視野で「人を育てる力」を未来へつなぐ一助となれば幸いです。