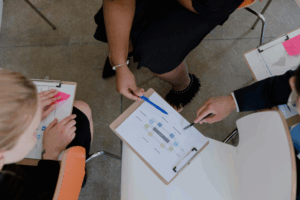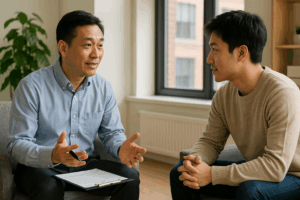アメリカで“コーチング”が注目される理由とは
教員は一般的にリーダーとしての資質を備え、学習者や同僚をより良い方向へ導く役割を担っています。こうした役割を考えると、教員の養成はリーダー育成の手がかりとなると言えます。また、教員養成は国の政策的側面が強く、リーダー育成に関する知見が豊富に含まれている分野でもあります。さて、教員養成といえば、「教育実習で教壇に立って経験を積む」──そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。ですが、近年アメリカでは、その実習の在り方に変革の兆しが見られます。その中心にあるのが、“コーチング”という考え方です。
今回は、アメリカの教育現場で進む「教員養成×コーチング」の流れについて、エレナ・アギラール氏の論考(Aguilar, 2013)を手がかりに、少しアカデミックな視点も交えながらご紹介します。
なぜ“コーチング”が注目されているのか?
従来のアメリカの教員養成では、「指導教員のもとで経験を積む」「大学の担当者が巡回する」といった実習モデルが主流でした。しかしその実態は、観察の機会が限られている、フィードバックが形式的・表面的などの課題があり、多くの教職志望者が「準備不足のまま教壇に立つ」という不安を抱えています。
さらに近年、教職をめぐる環境には構造的な問題が深刻化しています。たとえば、教員志望者の減少、新任教員の高い離職率(地域によっては3年以内に半数が離職)、そして低所得地域やマイノリティの多い学区における「成り手不足」や「定着の難しさ」などです。こうした課題を前に、今、求められているのは単なる「経験」ではなく、“続けられる教職人生”を支える仕組みです。
その中で再評価されているのが、“コーチング”という支援のかたちです。
“伴走型支援”としてのコーチングの力
インストラクショナル・コーチング(instructional coaching)は、単なる技術指導ではなく、「安心できる関係性の中で、実践を振り返り、試行錯誤を支えるプロセス」を提供します。特に新任教員にとって、コーチは「評価されないけれど、見守ってくれる存在」として機能し、燃え尽きの予防や定着率の向上につながると期待されています。
また、教職を志す学生にとっても、養成課程の早い段階からこうした伴走型の支援に触れることで、「教えること」への自信や自己効力感が育まれやすくなります。実際、そうした効果を示す研究も近年多く報告されています。
多様な学習者への対応が求められる今日、「誰かに相談できる」「ともに考えてくれる存在がいる」──このこと自体が、教員としての成長を支える大きな力になっているのです。
コーチングがもたらす3つの力
では、教員養成における“コーチ”とはどんな存在なのでしょうか?
エレナ・アギラール氏によると、コーチは単なる技術的なアドバイザーではなく、学校組織を丸ごと支える“変革の担い手”にもなり得ます。
1. 教師とともに考える「共感の伴走者」
コーチは教師を評価するのではなく、成長を支えるパートナー。
失敗や悩みを言葉にできる安全な場があることで、実習生は安心してチャレンジできます。
2. チームづくりを支えるファシリテーター
コーチは、教員同士の対話や協働を後押しする存在でもあります。
「話し合いがうまく進まない」「振り返りが形骸化している」といった場面でも、会議の設計や合意形成をサポートし、“学び合う文化”を育てていきます。
3. 組織変革を支えるミクロとマクロの橋渡し
一人の教師の成長支援から始まり、やがて学校全体の改善へと広がっていく──
これがコーチングの持つ本質的な価値です。コーチは現場と制度をつなぐ存在として、学校という組織の変革にも関与していくのです。
変化の鍵は「評価者」ではなく「支援者」
教育の世界では、「指導=評価」と見なされがちです。ですが、コーチは“教える”のではなく“引き出す”存在。
学び手である実習生が、自ら問い、悩み、試行錯誤できるように、「場」と「関係性」をデザインするのがコーチの役割です。
学校から見えてくる「支援型リーダー」の可能性
もちろん、アメリカの制度をそのまま日本に持ち込むのは難しいかもしれません。ですが、「安心して挑戦できる環境」「成長のパートナーとしての支援」という考え方は、日本の教員養成や学校現場にも通じるものがあります。
実はこの視点、教育だけにとどまらず、組織開発やリーダーシップ論でも注目されてきました。たとえば「ティール組織」や「学習する組織」の概念では、リーダーは「答えを与える存在」ではなく、「問いを開き、対話のプロセスを支える存在」として描かれます。
そう考えると、コーチはまさに新しいリーダー像を体現する存在ともいえるでしょう。
一方的に教えるのではなく、相手の経験や問いを引き出しながら、ともに考え、支える。
そのような“関係性の質”を土台とした支援のあり方は、学校という組織そのものを、よりしなやかで持続可能な「学びの共同体」へと変えていく可能性を秘めています。
参考文献・出典:
- Aguilar, E. (2013). The art of coaching: Effective strategies for school transformation. Jossey-Bass.
- Aguilar, E. (2014, October 7). How instructional coaches can help transform schools. Edutopia. https://www.edutopia.org/blog/instructional-coaching-transforming-schools-elena-aguilar
- Kraft, M. A., Blazar, D., & Hogan, D. (2018). The effect of teacher coaching on instruction and achievement: A meta-analysis of the causal evidence. Review of Educational Research, 88(4), 547–588. https://doi.org/10.3102/0034654318759268
執筆者プロフィール
藤村 祐子(ふじむら ゆうこ)
滋賀大学教育学系准教授・学長補佐(STEAM教育・リベラルアーツ担当)
兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科准教授兼任。日本学術振興会特別研究員、ミネソタ大学客員研究員などを経て現職。博士(教育学)。主な著書に「米国公立学校教員評価制度に関する研究」風間書房(2019)などがある。
南山教育研究所より|所長 南山紘輝のメッセージ
人を育てる営みは、単に知識を「与える」ことではなく、その人の内にある可能性を信じ、引き出していくことにあります。問いを重ね、共に考え、時に伴走しながら成長を支える。これこそが私たちの考える「本質的な教育」です。コーチングはそのための力強いアプローチのひとつですが、決して唯一の方法ではありません。時には別の手法がより効果的に働く場面もあります。だからこそ支援者には、多様なアプローチを柔軟に選び取り、相手や状況に応じて活用する力が求められます。本稿が、皆さまのコーチング実践をより豊かにし、人を支えるまなざしを広げる一助となれば幸いです。ともに学び合いながら、「人を育てる力」を未来へつないでいきましょう。