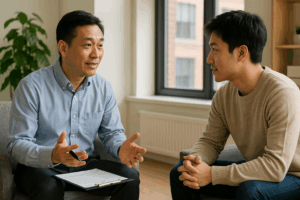はじめに:なぜコーチングが注目されるのか
これまでこのブログでは、さまざまな角度から「コーチング」をテーマに取り上げてきました。今回はその一環として、教員養成の文脈で実践されているコーチングに焦点をあてます。
一見すると教育現場に特有のテーマのように思えるかもしれません。ですが、実際に浮かび上がってくる課題──たとえば新任教師が「準備不足のまま現場に立たされる」ことや、十分な振り返りやフィードバックを得られないこと──は、企業や行政、NPO などあらゆる組織の人材育成の難しさと驚くほど共通しています。
だからこそ、教育分野で培われてきたコーチングの知見は、一般的なリーダーシップやマネジメントの現場にも応用可能です。単なるアドバイスや評価にとどまらず、「伴走しながら問いを投げかけ、相手自身の気づきと成長を促す」というアプローチは、どのような分野でも求められているのではないでしょうか。
今回は、アメリカの教育コーチングの第一人者エレナ・アギラールの著書 『The Art of Coaching』(2013)を手がかりに、人を育てるリーダーに役立つ視点をご紹介します。
『The Art of Coaching』とは?
本書は学校改革や教員支援の現場から生まれた実践知ですが、核心はより広い文脈に応用できます。アギラールはコーチングを「行動の修正」にとどめず、次のように位置づけます。
How(行動)だけでなく、Being(あり方)に働きかける。
個の変化をてこに、組織を“学びの共同体”へと変えていく。
テクニックよりも、関係性と問いの設計が成果を左右する。
教育でもビジネスでも、組織が難局にあるときに問われるのは、誰かの正解ではなく、関係性の質と学び続ける力です。本書はその設計図を提示します。
3つのコーチングモデル──状況に応じた関わり方の戦略
アギラールはコーチングを大きく3つのモデルに整理しています。これは「話し方の違い」ではなく、相手の状態・課題の性質・時間軸に応じて選ぶ戦略です。
1 Directive(指示型):即効性が必要なとき
このスタイルは、「今すぐ改善が必要な場面」において有効です。
たとえば新任教員が授業崩壊に直面している、あるいはチームリーダーが明らかに誤った判断を繰り返している……そんな時には、明確で具体的な指示や助言が求められます。
こんな時に使う:
緊急性が高く、安全や秩序が脅かされている
スキルや経験がまだ浅く、自己判断が難しい
相手が「今、何をすべきか」明確に知りたがっている
コーチの言葉例:
「次回の授業では、冒頭5分で学習目標をホワイトボードに書いてみましょう」
「会議では、最初に目的と時間配分を共有するとチームが動きやすくなります」
注意点:
このモデルばかり使うと、相手の自律性を奪ってしまう危険も。“緊急時の処方箋”として使い、脱却のタイミングを見極めることが重要です。
2 Facilitative(促進型):問いを通じて内面の気づきを育てる
ここでのコーチは、「知っている人」ではなく、「引き出す人」。
正解を与えるのではなく、「対話を通じて本人の中にある答えや可能性を見つけ出すこと」を重視します。
こんな時に使う:
– 相手がある程度のスキルや経験を持っている
– 自分なりのやり方を模索している
– 振り返りや内省を通じて学びを深めたいと感じている
コーチの言葉例:
「あの場面で、あなた自身はどんな意図を持っていたんですか?」
「もしもう一度やるとしたら、何を変えると思いますか?」
ポイント:
問いかけるだけでなく、「沈黙を待つこと」や「相手の言葉を受け止めて言い換えること」も含めて、促進型コーチングの一部です。
3 Transformational(変容型):深いレベルで“あり方”に向き合う
最も奥深く、かつ時間を要するモデルです。
ここでは、行動やスキルの習得を超えて、**相手の信念、価値観、自己認識に働きかけていく**ことが目的になります。
こんな時に使う:
– 成熟した実践者が「伸び悩み」や「意義の揺らぎ」を感じている
– キャリアの転機や役割変化の局面
– 組織文化の変容や長期的な成長をめざす場面
コーチの言葉例:
「あなたが“良い教師”だと思う条件って、どうやってできたんでしょう?」
「その不安の背景には、どんなストーリーがあると思いますか?」
このスタイルの本質は、“問いの深さ”と“関係の安全性”にあります。
短期的な成果は見えにくいかもしれませんが、本人の「在り方」が揺らぐ瞬間にこそ、深い変容が生まれます。
“使い分ける”ことが信頼になる
アギラールは、この3つのモデルを「どれかに固定する」のではなく、「相手の状態・文脈・関係性に応じて使い分けること」の重要性を説いています。
たとえば、最初はDirectiveでスタートし、信頼が深まるにつれてFacilitativeやTransformationalに移行していく──
それは、コーチとクライアントの関係が、「「指導する」から「伴走する」へと変化していくプロセス」そのものですアギラールは、この3つのモデルを「どれか一つに固定する」のではなく、相手の状態・文脈・関係性に応じて柔軟に使い分けることの重要性を強調しています。たとえば、新しい環境に不安を抱える相手にはまず Directive(指示型) で土台を整え、安心感が生まれたところで Facilitative(促進型) に移行し、最終的には Transformational(変容型) で本人の価値観や信念に働きかけていく──。このプロセスは、コーチとクライアントの関係が「指導する存在から伴走する存在へ」と深まっていく軌跡そのものです。
この考え方は、教育に限らずリーダーシップ全般に通じます。優れたリーダーは「常に答えを持っている人」ではありません。時に明確に方向を示し、時に問いかけによって考えを引き出し、そして時に相手の内面にある価値観をゆっくりと揺さぶる。状況に応じて関わり方を変えられる柔軟さが、組織の信頼と学びの文化を育てていきます。
つまり、コーチングの3モデルを使い分けることは、単なるスキルの選択ではなく、「人をどう信じ、どう育てるか」というリーダーの姿勢そのものを体現しているのです。リーダーが「指示する人」から「共に考える人」へ、そして「変容を支える人」へと変わっていくとき、チームや組織もまた、一方向的な指示待ち集団から、自律的に学び合う共同体へと進化していくのではないでしょうか。
信頼関係の構築は“静かなプロセス”
今回ご紹介した3つのモデルは、コーチングの「枠組み」を理解する第一歩です。
しかし、実際に使い分けをしていくためには、コーチと相手との間に信頼関係が築かれていることが不可欠です。
また機会があれば、本書の中でも特に重要なテーマ、
「信頼関係の構築は“静かなプロセス”」
──つまり、評価ではなく「問いの交換」を通じて育まれる関係性について掘り下げていきます。
参考文献
Aguilar, E. (2013). *The art of coaching: Effective strategies for school transformation*. Jossey-Bass.
執筆者プロフィール
藤村 祐子(ふじむら ゆうこ)
滋賀大学教育学系准教授・学長補佐(STEAM教育・リベラルアーツ担当)
兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科准教授兼任。日本学術振興会特別研究員、ミネソタ大学客員研究員などを経て現職。博士(教育学)。主な著書に「米国公立学校教員評価制度に関する研究」風間書房(2019)などがある。
南山教育研究所より|所長南山紘輝のメッセージ
教育の現場で培われたコーチングの知見は、実はすべての組織や人間関係に通じています。私が大切にしているのは、「人は本来、自ら成長する力を持っている」という前提ですだからこそ、リーダーや教育者の役割は「答えを与える人」ではなく、「問いと安心の場を用意し、共に歩む存在」へと変わりつつあります。エレナ・アギラールの示す3つのモデルは、その道筋を示す実践的なコンパスです。指示することから始まり、対話を通じて気づきを育み、やがては相手の“あり方”そのものを支える──このプロセスは、リーダー自身の変容でもあります。コーチングを学ぶことは、相手の可能性を信じる勇気を持ち、自分自身も学び続ける決意を新たにすることなのです。教育もビジネスも、組織の未来をつくるのは「人」です。静かに、しかし確かに信頼を育むコーチングの力を、ぜひそれぞれの現場で試していただければと思います。
南山教育研究所 所長 南山紘輝